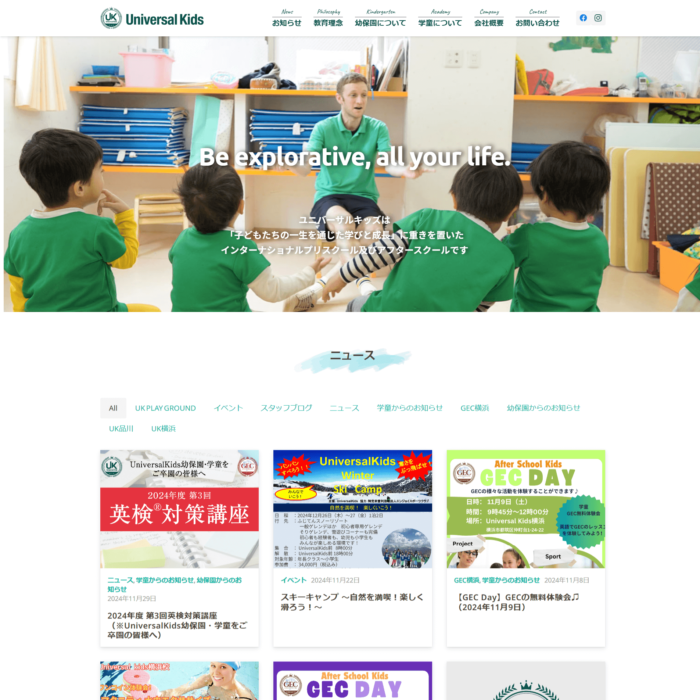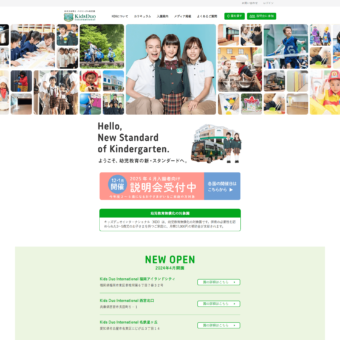発達障害やグレーゾーンの子どもはプリスクールに通える?注意点を解説

発達障害やグレーゾーンの子どもがプリスクールに通えるかどうか、気になっている保護者は多いでしょう。最近は子どもの特性に合わせたサポートがあるプリスクールも増えていますが、選び方や伝え方には注意が必要です。この記事では、発達障害やグレーゾーンの子どもの受け入れ状況や通うときのポイントをわかりやすく解説します。
発達障害・グレーゾーン児のプリスクール受け入れ状況
発達に気になるところがある子どもやはっきりと診断が出ていないグレーゾーンの子どもは、プリスクールに通えるの?と心配される方も多いでしょう。ここでは、実際の受け入れの様子や注意したいポイントをやさしくまとめました。
受け入れできるプリスクールはあるの?
発達障害やグレーゾーンの子どもでも、受け入れてくれるプリスクールはあります。とくに、少人数で一人ひとりに合わせた保育を行っているプリスクールや発達に関する知識がある先生がいるプリスクールは、サポート体制が整っていることが多いです。
一方で、受け入れを断られる場合もあります。プリスクールによっては、特別な対応がむずかしいという理由で、入園を断られることもあります。とくに「みんなと同じ行動を求める」プリスクールでは、子どもの特性に合わせるのがむずかしいことがあるようです。
グレーゾーンの子はどう見られる?
はっきりと診断が出ていない子、いわゆるグレーゾーンの子どもは、見た目では気づかれにくいことがあります。そのため、プリスクールによっては「わがまま」や「しつけの問題」ととられてしまうことも。
これは保護者にとってつらい状況です。だからこそ、最初の面談や見学のときに、子どもの特性をきちんと伝えることが大切です。サポートが必要な部分を共有することで、先生たちも準備がしやすくなります。
発達障害・グレーゾーン児をプリスクールに通わせるときの注意点
発達に特性がある子やグレーゾーンの子をプリスクールに通わせるのは、不安も多いものです。安心して通わせるためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか?ここでは、親として知っておきたい注意点をわかりやすく紹介します。
プリスクール選びはとても大切
まず大切なのは、子どもに合ったプリスクールを選ぶことです。少人数でゆったりと過ごせる、子どものペースを大切にしてくれる、先生が発達についての知識をもっているなど、子どもに合う環境を見つけましょう。
見学のときは、先生の声かけのしかたや子どもたちのようす、教室のにぎやかさなども見ておくとよいでしょう。静かな場所で休めるスペースがあると、子どもが気持ちを落ちつけやすくなります。
特性をきちんと伝える
プリスクールに入る前には、子どもの特性を正しく伝えることが大切です。「こんなときにパニックになりやすい」「急な変化が苦手」「集団行動がむずかしい」など、子どもの苦手なことやサポートが必要な場面を説明しましょう。
言葉で伝えるのがむずかしい場合は、メモにまとめたり、イラストや写真を使ったりして伝えるのもおすすめです。プリスクールと家が同じ方向を向いて子どもを見守ることで、安心して通うことができます。
子どもへの声かけや接し方
発達に特性のある子どもは、あいまいな言葉がわかりにくいことがあります。たとえば「ちゃんとしてね」「いいかげんにして」などではなく「イスにすわってね」「おもちゃをかごに入れてね」といったはっきりした言葉での声かけが効果的です。
また「よくできたね」「がんばったね」と小さな成功をほめることも大事です。成功体験が増えると、自信をもって行動できるようになります。
家でできる準備も大切
子どもが安心してプリスクールに通えるように、家でも少しずつ準備をしておくことが役立ちます。たとえば「プリスクールってどんなところ?」「お友だちと何をするの?」ということを、絵本や写真で伝えると、イメージしやすくなります。
また、時間の流れがわかりにくい子には、タイマーや時計を使って「あと5分で出かけるよ」と知らせてあげると安心できます。
無理せずに少しずつ慣らしていく
最初から毎日通うのではなく、週に数日・短時間からスタートして、少しずつプリスクールに慣れていく方法もあります。子どもが安心できるようになるまで、時間をかけることが大切です。
まとめ
発達障害やグレーゾーンの子どもでも、本人に合ったプリスクールを選び、特性に合わせたサポートを受けることで、安心して楽しく通うことができます。大切なのは、子ども一人ひとりの個性を大事にしてくれるプリスクールを見つけること。そして、保護者がプリスクールとの連携をとりながら、子どもの「できた!」を少しずつ増やしていける環境を整えることです。横浜市内にも、発達に理解のあるプリスクールや少人数でていねいに対応してくれるプリスクールがあります。いくつかのプリスクールを見学したり、地域の子育て支援センターや療育機関に相談したりすることで、よりよい選択ができるはずです。無理せず、ゆっくりと、子どものペースを大切にしながら探していきましょう。








-トゥインクル・キッズ-1.png)